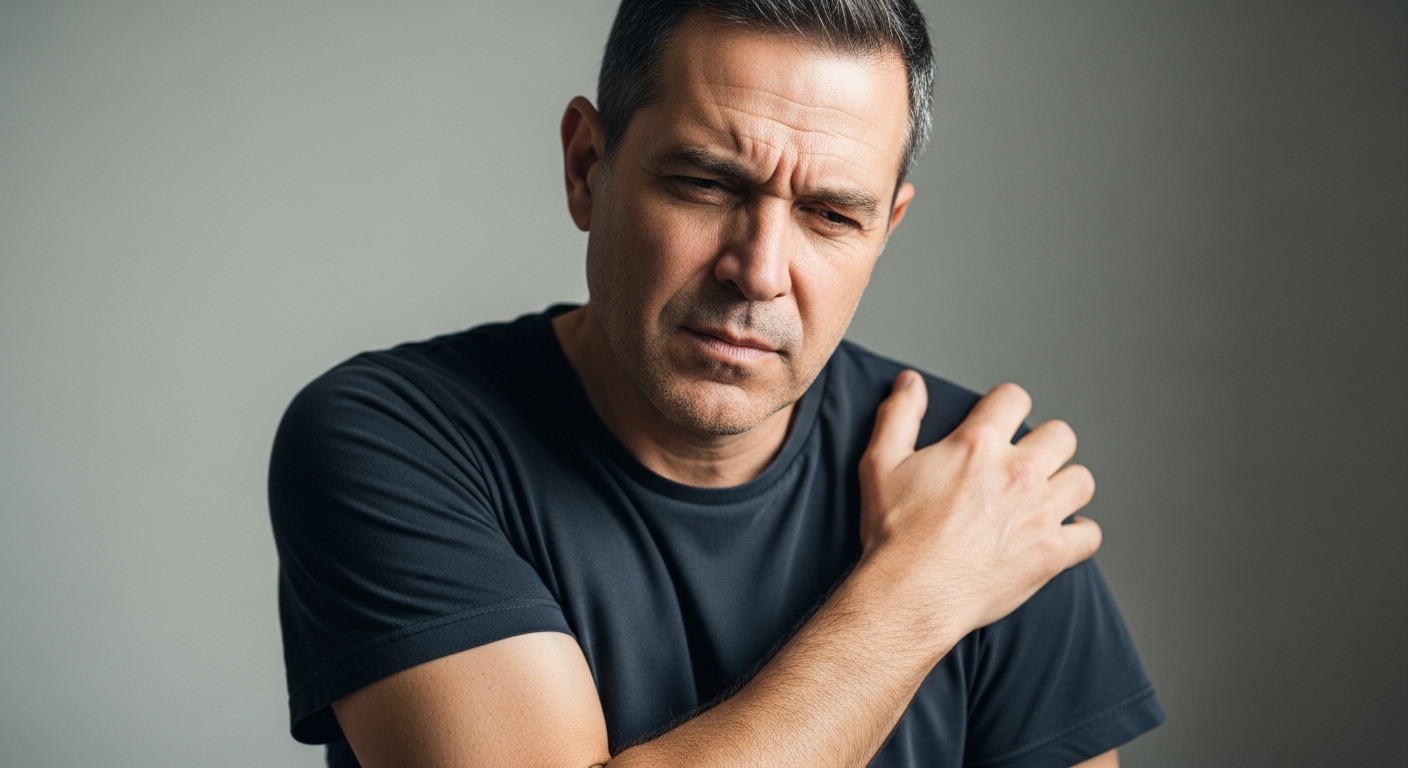接骨院にも狭心症の疑いのある患者さんが、間違えて来院されるケースがあります。
患者さんご本人は「腕の痛み・怪我」「背中の痛み・怪我」と勘違いし来院されることが多いです。
一般的な怪我の症状とは大きく異なり、下にまとめたような特徴的な症状が見られます。
狭心症の疑いがある患者さんは、すぐに医療機関を受診するようにしてください。※接骨院では、当然、治療等、行うことができません。
以下、簡単ではありますが、狭心症の情報をまとめておきます。
腕や背中の怪我と間違えて来院されやすい「狭心症」
狭心症の種類
狭心症は、症状の現れ方によっていくつかの種類に分けられます。
- 労作性狭心症(安定狭心症)
- 階段の上り下り、早歩きなどの身体活動や、精神的なストレスがかかった時に心臓が酸素を多く必要としますが、冠動脈が狭くなっているために十分な血液が供給されず、胸痛などの症状が現れます。
- 安静にすると数分以内(長くても5分以内)で症状が改善するのが特徴です。
- 冠攣縮性狭心症(異型狭心症)
- 冠動脈が一時的にけいれんして狭くなり、血液の流れが悪くなることで発作が起こります。
- 安静時、特に夜間や早朝に症状が出やすいのが特徴です。飲酒や喫煙が誘因となることもあります。日本人に比較的多いタイプと言われています。
- 不安定狭心症
- 労作性狭心症が悪化した状態で、今までよりも軽い動作で症状が出たり、安静時にも症状が出たり、発作の回数が増えたり、持続時間が長くなったり、ニトログリセリンの舌下投与が効きにくくなったりします。
- 心筋梗塞に移行するリスクが高く、緊急性が高い状態です。
原因
狭心症のほとんどの原因は、動脈硬化です。動脈硬化とは、高血圧、脂質異常症(高コレステロール血症)、糖尿病、喫煙などの要因によって血管が柔軟性を失い、硬くなったり、血管の内壁にコレステロールなどが沈着して「プラーク」と呼ばれるコブができ、血管が狭くなる状態を指します。
その他、まれな原因として、重度の高血圧、大動脈弁狭窄症、肥大型心筋症なども挙げられます。
症状
狭心症の代表的な症状は以下の通りです。
- 胸痛、胸部圧迫感: 「胸が締め付けられる」「胸が押さえつけられる」「胸が焼け付くような感じ」などと表現されます。
- 放散痛: 痛みが胸だけでなく、左肩から腕にかけてのしびれや痛み、背中の痛み、顎から首へのしびれや痛み、歯が浮くような感じとして現れることもあります。
- 息切れ、動悸: 心筋への血流障害によって不整脈が生じたり、息切れを感じたりすることがあります。
- 吐き気、冷や汗、めまい、失神発作: 血流不足が重症化するとこれらの症状を伴うことがあります。
これらの症状は、特に運動時や精神的ストレス時に現れ、安静にすると数分で治まるのが典型的なパターンです。ただし、不安定狭心症の場合は安静時にも症状が出たり、症状が長く続いたりします。
検査・診断
狭心症が疑われる場合、以下のような検査が行われます。
- 心電図検査: 心臓の電気的な活動を記録し、虚血による波形の変化を確認します。安静時の心電図では異常がないことも多いため、運動負荷をかける「運動負荷心電図検査(トレッドミル・エルゴメータなど)」が行われることもあります。
- 心エコー検査(超音波検査): 超音波を用いて心臓の動きを直接観察し、血流障害による心臓の壁の動きの低下などを確認します。
- 血液検査: 心筋の障害を示す酵素(CK、トロポニンなど)や、心不全のマーカー(NT-proBNP)などを調べます。
- 胸部レントゲン検査: 心臓の拡大や肺うっ血の有無などを確認します。
- 負荷心筋シンチグラフィ: 放射性同位元素を注射し、心筋の血流の状態を画像で確認します。運動や薬剤で心臓に負荷をかけて行います。
- 冠動脈CT検査: 静脈から造影剤を注入し、X線で冠動脈の狭窄の程度や部位を詳しく調べます。比較的低侵襲で詳細な画像が得られます。
- 心臓カテーテル検査(冠動脈造影): 足や腕の血管からカテーテルと呼ばれる細い管を挿入し、冠動脈に直接造影剤を注入して、血管の狭窄の有無や程度、部位を最も正確に診断できる検査です。必要に応じて同時に治療を行うこともあります。
治療
狭心症の治療は、病状や原因、患者さんの状態によって薬物療法、心臓カテーテル治療、冠動脈バイパス手術が適切に組み合わされます。
- 薬物療法:
- 狭心症発作の緩和・予防: ニトログリセリン(舌下錠)は、発作時に血管を拡張させて症状を和らげる効果があります。発作が起こったときにすぐに使えるように携帯します。
- 長期的な病状の管理:
- 抗血小板薬(アスピリンなど): 血液をサラサラにして血栓ができるのを防ぎます。
- β遮断薬: 心臓の拍動を抑え、心臓の酸素需要を減らします。
- カルシウム拮抗薬: 冠動脈を広げ、血液の流れを改善します。冠攣縮性狭心症の治療に特に有効です。
- 硝酸薬(長時間作用型): 血管を拡張させて心臓の負担を減らします。
- ACE阻害薬/ARB: 血管を広げ、血圧を下げ、心臓の保護に役立ちます。
- スタチン系薬剤: コレステロール値を下げ、動脈硬化の進行を抑えます。
- 狭心症の原因となる高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の治療も同時に行われます。
- 心臓カテーテル治療(経皮的冠動脈インターベンション:PCI):
- 足の付け根や手首の血管からカテーテルを挿入し、狭くなった冠動脈まで進めます。
- 先端にバルーン(風船)のついたカテーテルで血管を広げ、多くの場合、金属製の網状の筒である「ステント」を留置して血管を内側から支え、再狭窄を防ぎます。
- 身体への負担が比較的少なく、入院期間も短いのが特徴です。
- 冠動脈バイパス手術(CABG):
- 狭くなったり詰まったりした冠動脈の先に、別の血管(自身の胸の動脈や足の静脈など)をつなぎ合わせて、血液の新しい通り道(バイパス)を作る手術です。
- 複数の血管が広範囲に狭くなっている場合や、カテーテル治療が難しい場合に選択されます。心臓カテーテル治療に比べて身体への負担は大きいですが、より根治的な治療となる可能性があります。
予防
狭心症は動脈硬化が主な原因であるため、動脈硬化の進行を抑えることが予防の基本です。
- 禁煙: 喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進する最大の危険因子です。禁煙は狭心症予防に最も重要です。
- 生活習慣病の管理:
- 高血圧: 適切な降圧薬の使用と、減塩(1日6g未満)、適度な運動、ストレス管理などで血圧をコントロールします。
- 脂質異常症(高コレステロール血症): 飽和脂肪酸やコレステロールの摂取を控え、青魚などに含まれる不飽和脂肪酸を積極的に摂りましょう。必要に応じて薬物療法を行います。
- 糖尿病: 血糖値を適切にコントロールすることが重要です。
- 肥満: 適正体重の維持が重要です。
- 食生活の改善:
- 脂質、塩分、糖分を控えめにし、バランスの取れた食事を心がけます。
- 野菜、きのこ類、海藻類、果物など、食物繊維やビタミン、ミネラルを多く含む食品を積極的に摂りましょう。
- 大豆製品(豆腐、納豆など)も心臓病予防に役立つとされています。
- 適度な運動:
- 無理のない範囲で有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)を継続的に行います。ただし、狭心症の症状がある場合は医師と相談し、運動内容を調整しましょう。
- ストレス管理:
- 精神的なストレスも狭心症の発作を誘発する要因となるため、ストレスを上手に解消する方法を見つけましょう。
- 定期的な健康診断:
- 動脈硬化のリスク因子(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)を早期に発見し、治療につなげるために、定期的に健康診断を受けましょう。
狭心症は心筋梗塞に移行する可能性もあるため、胸の痛みや違和感など、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが大切です。